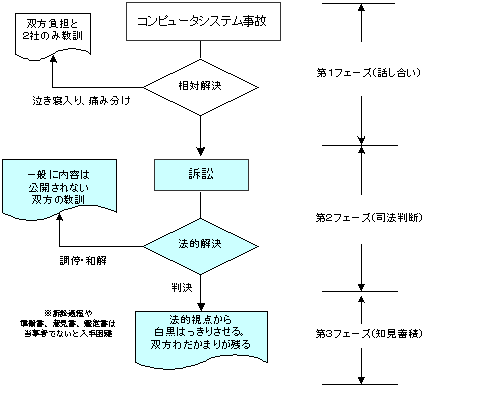
IT�V�X�e���i�ׂƐ��̍ٔ��O���������iit-ADR�j ISSN 2187-5049 Vol.05 2014-02-27�@(c)naoki.inagaki
�P�FIT�i�ׂ̌���
�@�@�E�葱���̗���Ɖۑ�
�@�@�EIT�i�ׂ̔����̏�
�Q�F�w���߂��Ɓx������i �@�u�m�̓����v
�@�@�E�ٔ����@�ƍٔ��O�̕��������iADR�j
�@�@�E����@���̕č��ł���o�����s�҂̍ٔ�����
�R�F��含����ADR
�@�@�E�`�c�q�̌���
�@�@�E�����������@�̑S�̑�
�S�FADR�ƍs���i�׃v���Z�X
�@�@�E�s���i�ׂ̈ʒu�Â��Ɖۑ�
�@�@�E�d�g�s���i�ׁiPLC�ًc�\���R���j�ɂ݂��Y�ߒ�
5:�����Ȉ���v�ł��邪�A����I�����R�c��i�̖閾���I
�@�@�E�m�����ق̈ӌ���W
�@�@�E�č����O���[�g���[����̃v���Z�X�̋��P
�P�FIT�V�X�e���i�ׂ̌���
�uIT�i�ׁv�Ƃ́A�����ٔ��œ��ɃR���s���[�^�E�V�X�e���ɌW��i�ׂ��ď̂���B
�����ł́A�\�t�g�E�G�A�J���A�\�t�g�̔[���x���A�[���\�t�g�̕i���i���r�����݂���v���O�����̖��j�A�V�X�e����Q�⎖�́A�V�X�e���^�p�ێ�A�v���W�F�N�g�ڍ���V�X�e���̖@�I�R�͖ʂ̌��ؓ�����ٔ��ɂȂ�A������������\�Ȕ͈���1-1�Ŏ����ɕx�ނ��̂𒆐S�Ɏv�l����B
���i�ׂ̗���
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@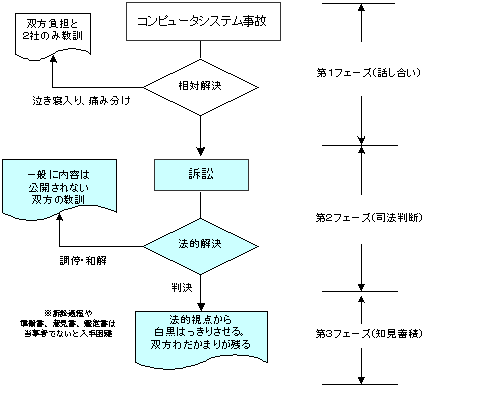
�@
IT���̂��A�����Ȃ�ٔ������ɂȂ邱�Ƃ͏��Ȃ��B�����̏ꍇ�v���O����������IT�x���_�[�Ǝ҂ɐ����_��⏀�ϑ��_��őo�����W����Ă���A����́u�ȐS�`�S�̎Љ�v�ł��������Ďd�������Ă���̂Ŏ��̂〈���݈Ⴂ���\�ʉ����Ă��A�]���̊�Ƌ��e�x�����ꍇ�ɂ̂ݑ�3�҂ɔ���������ƂɂȂ�B
IT���ɂ���Ă͈�̎咣�łP�`�Q�����v���邱�Ƃ������A�R���S�͎̂��Ăɂ�蒷���Ԃ�v���A���ʓI�ɋZ�p�I�[�����������Ȃ��P�[�X�������B�R���ŏI�i�K�Œ����a���̓�������@�I�ȃ��[������������Ă��Ȃ�����iIT����ɂ����閯�i�@�̖������Ɩ@���E�ɌW���IT���Ɛl���w�̔����j�ł́AIT�Z�p�����ɏœ_���i�����i�ו։v�͎��Ă��Ȃ��p������B
�i�ׂ̓��e���R���s���[�^���̂Ȃ��ł��\�t�g�E�G�A�E�v���O�����ɋN������Č��A������v���O�����쐬�i�K�ł͌���Ȃ��z��O�̃g�����U�N�V�����̐U�镑���ȂǁA�J���i�K�ł͗\�z�E�\�m������Ȕ�@�\������1-2�̎��̂��ڗ����Ă��Ă���B�@�@�@�@�@�@
��IT�i�ׂɂ݂�u���v�̍��
�i�҂́A����R���s���[�^��������Â炢���ŗ�����K�v����A���̔�Ώ̐������݂���B
IT�́A�ڂɌ����Ȃ������Ɍ����N�i��ⓚ�ُ��쐬�ő���ȓw�͂�v����i�R���s���[�^�Z�p���悭�m����ٌ̕�m��ٔ����̑w�������j��i�܂œ��ݐ�Ȃ��̂ł���B�܂��Đ^�̌������������߂�Z�p�_��V�X�e���I������Nj�����̂����_�ɂȂ�P�[�X�͏��Ȃ��B
�܂��A�i�@���߂Ə������o�̑��Ⴉ��R���s���[�^���̂̎����F��̍�����̖ʂ��烆�[�U�[����̑i�ׂ́A���ؒi�K�ō�����ɂ߂�A�i����͋��ZIT�i�ׂɌ��炸�A���Q�i�ׂ�s���i�ׂȂǏ���ҁE���[�U�[���i���鍢��ɗގ��j�i�ג�N�̒i�K�ŁA�����Ԃ̘J�I���S��_��肩��o�ϓI���������f������߂邩�A�����Q���肷��̂����̂ł���B
�@�I�Ȍ����́u�i�@������v�ƃV�X�e���v�l���S�́u�Z�p������v���璭�߂������A���̂ɑ��錩�����A���{�I�ɈقȂ��Ă���Ƃ���ɁA�����𖾂�v�����͂܂ł��ǂ���Ȃ��ł���p������B�v���O�����́u�o�O�v���\�t�g�̌��ׂł���Ƃ����邽�߂̗v�����m�肵���悤�Ȕ���͗�O�ł���B
�Z�p�I��������Z�p�_�����������^���ʂ�����g�ݑ��_�ɂȂ�ƁA�u�[���v���O�����̎����F�莖����1-3�v�̂悤�Ƀv���O�������r���Ɩ��ɂǂ̂悤�ȉe����^���邩�A���ꂪ�ǂ̂悤�ɖ@�I�ȈӖ��������̉��ߐR�����o�āA�����܂Ŗ�T�N�̍Ό������������������B�����Ă���́A���҂Ƃ����ʂ̔[���������Ȃ��A�������肢���Ȃ��㖡�̈������ʂ��c����̂ł�����B
���̏������o�Ƃ̂���Ⴂ�́A�u�����������Ƃ��đf�p�Ɍ��Ă���̂ł͂Ȃ��B�嗤�@���i�ƁA���A���Ȃ��j�̖@�����Ƃ́A�@���̖̏@���v���Ƃ����X�N���[����ʂ��āA�p�A�Ė@���̖@�����Ƃ́A���̖@���Ƃ����X�N���[����ʂ��āA�������݂�B��-�S�v�B���ƂɈˋ����Ă��̂łȂ����B�@�����͎��R��`�Љ�Ōo�ϊ�����IT�Z�p�AIT���i�̓�����܂�ɂ��A�����J�����i����@�Љ�F����čٔ������o��ł��̗L���ȃI�����W�ٔ������ďo����j�ɓł���A�����ٔ��ƂȂ�Ƒ嗤�@���o�ōق��Ƃ���ɗ���������̂łȂ����B
���āhLaw School�h�Ɠ����p����g���Ă��i�ړI�͓����悤�ɗD�ǂȖ@���l���琬����ɂ��邪�j�̃J���L�������݂�Η�R�ł���B�č��͂܂��ŏ��ɐl�Ԑ��̊m��������A���̌�Ɂu����v��@���ɂ�ނ��A�ɓ������łĂ���B�{�M�͐����@�Љ�ł���̂ŁA�܂��𗝉�����Ƃ��납��n�܂�̂ł���B
���̗l�ɁA�i�ׂ͈�ʖ��������ɑ����Č��ʓI�ɁuWin-Win�̊W�v�͒z���ɂ������̂Ƃ���Ă���B
���Z����ɒ��ڂ��ׂ�����I�Ȗ@�������������B�i�ׂɂ����āA�ǂ��炪�����ׂ��ł��邩�̓_�ł���B���ؐӔC�`���Ƃ��ẮA�w�d�q�L�^���@�x�ɂ݂���d�q���L�^�@�֑������ߎ��ł��������Ƃ�d�q���L�^�@�ւ��ؖ����Ȃ�����A�d�q���L�^�@�ւ����Q�����ӔC�����ƂƂ��Ă���_�ɂ���B�i���@�́A14���j
���̂��Ƃ́A�d�q������嗬�ƂȂ��čs�������̂Ȃ��ŁA�]���̍s���ɏ]���Ă���Έ��ׂ̎��ォ��A���瑊��ڋq�i��Ɓj�ɑΛ�����}�C���h�������˂Ȃ�Ȃ�����֕ϑJ�̃X�^�[�g������A����I�]���_�ɂ��Ă��邱�Ƃ������Ă���B
���̒��Łu�Ђ��v�Ɓu�������Ɓv�͏��Ȃ��ق����悢�B
�����O�ɐ�᎖���̋��P���҂�݂āu�\�h�v��S�������̍Ĕ��h�~����d�v�ł��鎖��g�D���S�̂��ĔF������̂���̌��p�ł��낤�B
��1-1�@��������Ă��锻��͖�8���ł���B�ٕM�w���pDB�ɂ݂�`�ԑf��͋Z�@�̌��x����w��IPSJ�EIP26�A2005/1/20
�@�@�@�@�����P�N���璼�߂܂Ŗ�60����IT���Ⴊ����B�i�l���֘A�A�C���^�[�l�b�g�I�[�N�V�����֘A�A���쌠�֘A�������j
��1-2�@��@�\�G�v���O�����쐬�i�K�̋Ɩ��@�\�̐ÓI�Ȏd�l�ɑ��āA�@�B�����ғ�����������ŋN���鏈���ʃI�[�o�[��v���O���������\�͗̈�ُ̈�
�@�@�@�@�Ȃǂ̓��I�Ȏd�l�͈͂���悤�ȃP�[�X���w���B
��1-3�@�����n��16�12�22�@��10�i���j23871���G�����_��Ŕ[�������v���O�����̓��݂������r�́A�ϑ����̎d�l��肩�A�C����Ɣ͈͂��̑��_�ŁA
�@�@�@�v���O�����́u�o�O�v���\�t�g�̌��ׂł���v�����`���A���؎�����ʂ��v���O�����Ɍ��ׂ�����ƔF�߂�ꂽ�����i���^No.964�@172�Ŗ��@635���j
��1-4�@�w�@���w�x��Q��2.2.2�ٌ�m�̖����@����R�E���Y�D�����@�L��t���@58��
�E�{�MIT�V�X�e���i�ׂ̔����̏�
�@�@�@�@�@���̕��́A���g�o���i�����X�V�ׁ̈j�ʌf���܂���
�@�@�@�@���u�Q���FIT�V�X�e���ɌW���i�ׁiit�ٔ�����j�v
![]() ���̃y�[�W�̐擪��
���̃y�[�W�̐擪��
�Q�F�w���߂��Ɓx������i�@�m�̓���
�@�E�ٔ����@�ƍٔ��O�̕��������iADR�j
�ٔ����ōs����ٔ��́A�@�����Ƃ̎d���̒��S�Ɉʒu����B���ꂩ����ٔ����ƍٔ��̂��d�v���͑傫���ς�邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B
�������A�ٔ��͓`�Ƃ̕ł��蔲���Ȃ��Ƃ���ɈӖ�������Ƃ����T�O���������̂����Ă���B���̊T�O�́A�������ٔ��ɂ܂ōs���Ȃ��Ƃ���ŏ�������̂��]�܂����Ƃ����O��ɗ����Ă���B�����A���̂悤�ȍl�������˗��l�������̂ł���A�@�����Ƃ͈˗��l�̈ӌ��ɓY���āA�������ٔ��ɂ����ɍٔ��O�Ō���������w�͂����߂���B
�A�����J�ł��A�i�ׂ��ĉ����ł��Ȃ����Ƃ�����Ƃ����F���̍��܂�ɔ����āu�ٔ��O�̕��������iADR�GAlternative Dispute Resolution�j�v�ƌĂ�镴���������@���]������A�ٔ��Ɩ��ڂȘA�W��ۂ��Ȃ��畝�L���������}���Ă���B�ٔ��̌��E�Ƃ��Ă����Ύw�E�����̂́A�l�������ʂ̂悤�Ȗ��ł́A���̉����ɂ͊W�ҊԂ̑��ݗ�����ӎ����v�����ߎ�ɂȂ�̂ɁA�ٔ��͑��Q�����┱������邾���ł����āA���̖{���̉����ɂ͂Ȃ���Ȃ��Ƃ����_�ł���B
���ׂČ��J�������̍ٔ��ł́A���Q�҂Ɣ�Q�҂̑o���Ɋւ��鎖�����L���m���邱�ƂɂȂ�Ɠ����ɁA�����ҊԂ̊W���G�ΓI�Ȃ��̂ɂȂ肪���Ȃ��߁A�����I�Ȑl�ԊW�̉��P�ɂ͂Ȃ���ɂ����B
���̂悤�ȍl���̌��ʁA�p���I�Ȑl�ԊW�̗v�f���܂܂��u�����ߖ��v�u�����Ȍٗp�@��̕ۏ�v�u�l���i��v�u�Z�N�n���v�Ȃǂ̗̈悾���łȂ��A�����I�ȑŎZ�������u�����@���v�܂ł���ADR�̑ΏۂƂȂ��Ă��Ă���B
---���̍��́w�@���w�x����R�E���Y���@�L��t���@4.3�@160�ł��̂܂܈��p---
�����āA����ADR��@�͑����ԂɌׂ鏤���@������ł��A�n�[�O���ۖ@�ŕ��������̕W����i�Ƃ��č��ەW���ɋK�肳��Ă��āA���܂�ADR��i�̊��p���m�b�̂ЂƂƂ��Ċ��p����Ă���B
�_�k�����ł���{�M�̏����ӎ����炩�A�ٔ��͉����F���ł������i���͎q���̂���A�e������ٔ������͂����b�ɂȂ�ȁI�ƌ�炳�ꂽ�j�B
�ٔ���i���A�G�W�v�g�×��l�ނ̔����i�ŋ��ɂ̉������@�E��i�Ƃ��Ă��A��͂����߂Ȃ��̂������ł���B
�C��R�����x��ADR���x
�C��R�����x�́A���I�m���ғ��u�Łu�^�̌�����T�����A������Ɍ��т������������o���㐢�ɒq�b���c���Ƃ���v�ɁA�ٔ����x�ƈႢ�����肻�ꂪ�ٌ��ł���A���ٌ̍����S�����҂̔[���ɍs�����Ƃ��ǂ���E�E�E�E�Ǝv���Ă��܂������A�w�������Փˁx�����ŁA�l�����ς��n�߂��B
�C��R�́A2009�N1���u�������ɉ���`�����������v�ƔF��ٌ������B�����Č��q�C���̐ӔC�͖��Ȃ������B
���A���l�n�ق̓W�J�́A�܂������������W�J�ŁA���̌��q�C���̐ӔC�`�������_�ƂȂ��Ă���B
���������ڂ���邪�A�C��R�́u�^���̒Nj��v�ƁA�ٔ����x���̒n�ق́u�^���Nj��̓����v�ł́A�o���_������Ȃɂ�����Ă��Ă���B
��HP�ł��A��ʎ��̂ɑ���u���̐��ψ���v���l�A��������Ă��Ȃ��C�̏�ł̑o���̌������̈Ⴂ�������f�ł��Ȃ��؋��i�ޗ��j�̂Ȃ��Łu���ψ��v�����A������Ȃ��S�̃`���l���`�����ł���E�E�E�E�ƐM���Ă����B��Éߌ��IT�������A�C��R���l�́u���R�c�v�̏ꂪ�]�܂����E�E�E�E�Ƃ������Ă������A��������ł́A�čl����@��ƂȂ낤�B
�i�L��2011/01/24���݁j
�@(����e2011/01/9�j
�@��ʎ��̒��������ψ���iJR�����{�ɂ݂�X�ԁj
�@
<��>
�{�M�`�c�q�i�ٔ��O���������葱�j�̌���Ɖۑ��F2008�N11��5���@���n���ٔ����ψ���@�R�c��
�@
![]() ���̃y�[�W�̐擪��
���̃y�[�W�̐擪��
�E����@���̕č��ł���o�����s�҂̍ٔ�����
�x���_�[�Ƃ̓D���̓���������邽�߂ɁACIO���Ȃ��ׂ�����
���[�U�[�ƃx���_�[�Ƃ̊W���O��I�ɂ�����Ă��܂��A���̍s��������́u�i�ׁv�Ƃ������ƂɂȂ�B���ɕč��ł́A�����ɂ��āA�\�t�g�E�F�A�E�v���W�F�N�g�̎��s�ɂ܂��i����������I�ɑ��債�Ă���B�ٔ��́A�\�������҂Ɣs�҂����߂���̂ł͂��邪�A���Ƀr�W�l�X�ւ̃C���p�N�g���傫���A�����z�������IT�v���W�F�N�g�̏ꍇ�A�@��ő����Ă������ґS�����u�s�ҁv�ɂȂ邾���ł���B�ł́A�D���̓���������邽�߂ɁACIO�͂ǂ�ȓ_�ɒ��ӂ��ׂ��Ȃ̂ł��낤���B�{�e�ł́A���ۂ̎����ٌ�m�̈ӌ��Ȃǂ�D������Ȃ���ACIO��������ׂ��i����p���Љ�悤�B
�X�R�b�g�E�x���i�[�g�@text by Scott Berinato�K���������͂��́g�������h

U.S.�J���Ń}�[�P�e�B���O�S�����В����O���[�o��CIO�߂�V�F���[���E�N�C�b�V�����B���́A����IT�v���W�F�N�g����@�ɕm�����ہA����g����l�h�ƂȂ�A�x���_�[���Ƃ̊W�C�����ʂ��������т����Bphoto by Jeff Sciortino
�@2000�N3���A�����N��15���h���̑��Ζ����w��Ѓg�����X�A���j�A�́A�\�t�g�E�F�A�E�x���_�[�̃g���v���E�|�C���g�E�e�N�m���W�[�Ƃ̊Ԃł���_������킵���B����́A�g�����X�A���j�A��27�̎��Ə����ׂĂ��g���v���E�|�C���g�̓d�q������v���b�g�t�H�[���uTempest 2000�v�ŘA�g������Ƃ������̂��B�_��ɂ́A�V���ɓ�������Tempest�ƁA�g�����X�A���j�A�����łɉ^�p���Ă����s�[�v���\�t�g�̉�v�V�X�e���Ƃ�����6�{�̃C���^�t�F�[�X���A�g���v���E�|�C���g�����v�^�J������Ƃ������������荞�܂ꂽ�B
�@�g�����X�A���j�A�ɂ��Ă݂�A���̃v���W�F�N�g�́A���ԈˑR�Ƃ����u�I�[���h�E�G�R�m�~�[�v����A21���I�^�́u�C���^�[�l�b�g��Ɓv�ւƒE���}�邽�߂�1�̑傫�Ȃ����ł������B���ɓ��Ђ̌o�c�w�����O���Ă����̂��A�V�����v���b�g�t�H�[���Ɗ����̉�v�V�X�e���Ƃ̘A�g�ł������B������24 ����365�����A���^�C���ŏ��������ł����Ƃ��Ă��A���ꂪ��v�V�X�e���ƘA�g���Ă��Ȃ���A���̖��ɂ������Ȃ����炾�B
�@���������g�����X�A���j�A���̐S�z�ɑ��A�g���v���E�|�C���g�͎��M�����Ղ�Ɂu�C���^�t�F�[�X�͗e�ՂɊJ���ł���v�Ƒ匩������Ă����B���̍����Ƃ��ăg���v���E�|�C���g�����������̂��g�o���h�ł���B���Ђ́A���łɐ��Ђ̌ڋq�ɑ��ē���̃C���^�t�F�[�X���J�������o�������邱�ƁA���̒��ɂ̓g�����X�A���j�A�Ɠ������w�ƊE�̃~�G�R�ɔ[������Tempest�ƃs�[�v���\�t�g�̃V�X�e���Ƃ�����C���^�t�F�[�X�����܂�Ă��邱�ƂȂǂ������āA�g�����X�A���j�A����M�p������������̂ł���B
�@�g�����X�A���j�A���́A�_�ɃT�C������ƂƂ��ɁA�g���v���E�|�C���g�̃v���X�����[�X�Ɏ��Ж����f�ڂ��邱�Ƃ������A�č��̊e���f�B�A�́u�ω��̌������s��Ō����I�Ȏ��ƌo�c�v�Ƃ��������t�ŁA���̃v���W�F�N�g���������Đ�`�����B���̎��_�ł́A���ꂪ�ǂ����Ă��K���ȁg�������h���̂��̂ł������B�����Ƃ��A�s�K�Ȍ������Ȃǂ��̐��ɂ��肦�Ȃ��B���͌���������Ȃ̂�����B
�@���_���猾���ƁA�g�����X�A���j�A�ƃg���v���E�|�C���g�́g�����h�́A����Ȍ������}�����B
�@��ɂȂ��ĕ����������Ƃ����A�g���v���E�|�C���g�́A����̍ő�̋��݂ł���Ƃ��Ă����g�o���h�����Ȃ�֒����Ă����B����A�֒��ǂ���ł͂Ȃ��B���̂Ƃ���A���А��i�Ƒ��А��i�Ƃ��Ȃ��C���^�t�F�[�X������J���������ƂȂ�1�x���Ȃ������̂ł���B���ЂɂƂ��Čo���ƌĂׂ�悤�Ȃ��̂�����Ƃ���A�������Ǝ҂��g���A���̃}�l�W�����g���肪�������Ƃ��킸��2�x���邾���ł������B
�@�g�����X�A���j�A���琿���������v���W�F�N�g�ɂ��Ă��A�g���v���E�|�C���g�̓C���^�t�F�[�X�����ЂŊJ������C�Ȃǂ��炳��Ȃ��A���̍�Ƃ��������܃s�[�v���\�t�g�Ɋۓ��������B���̂����A�_�܂Ƃ܂��Ă��甼�N�߂����o�߂���2000�N8���ɂȂ��Ă��A�s�[�v���\�t�g�ɑ��Ė��m�ȃv���W�F�N�g�v����������A�C���^�t�F�[�X�J���̐i�����܂Ƃ��Ɋē��Ă��Ȃ��Ƃ������A������ȑΉ��ɏI�n���Ă����̂ł���B
�@�������āA�_��Ŕ[���ƒ�߂�ꂽ2000�N12��31�����}���Ă��A�{��6�{������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��͂��̃C���^�t�F�[�X�́A1�{����Ƃ��������Ă��Ȃ������B���̎���ɏł����g���v���E�|�C���g�́A�J���x��̐ӔC���s�[�v���\�t�g�ɉ������A���Ђւ̎x�������~�B���̐�����A�g�����X�A���j�A���g���v���E�|�C���g�ւ̎x�������X�g�b�v�����B
�@�g���v���E�|�C���g�́A�������M�p�����悤�ƁA��2001�N��3��9���܂łɂ��ׂẴC���^�t�F�[�X��K����������悤�A�s�[�v���\�t�g���Ɋm���������ŁA���炽�߂Ă��̎|���g�����X�A���j�A�ɕB���Ԃ͂Ȃ�Ƃ����E�Ɍ��������Ǝv��ꂽ�B�����A��x�����Ă��܂������Ԃ����ɖ߂��̂͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B���̌�A3��29���A4��24���A4��30���Ɨ��đ����ɔ[�����������ɂ�������炸�A�C���^�t�F�[�X�͊������邱�Ƃ͂Ȃ������B�����̌_��ł́A37��5,000�h���̉��i��6�{�̃C���^�t�F�[�X��[������Ƃ���Ă������A400�����o�߂��A�������̋��z��63��5,000�h���ɒB���Ă��A�g�����X�A���j�A����ɂ����C���^�t�F�[�X�͂킸��1�{�����ł������B
�@�g�Ō�ʒ��h�Ƃ��Ē������N8�����{�̔[���ɂ��A�C���^�t�F�[�X�̉ғ����Ԃɍ���Ȃ����Ƃ����炩�ɂȂ������Ƃ��A���Ƀg�����X�A���j�A�́A�g���v���E�|�C���g�ɑ��邷�ׂĂ̎x���������ۂ��邱�Ƃ����f�����B����ƁA�g���v���E�|�C���g�́A���̍s�����_��ᔽ�ł���Ƃ��āA���łɒς݂̃T�[�r�X�ɑ���79��5,000�h���̎x���������߂�i�����N�������̂ł���B�������A�g�����X�A���j�A�����ق��Ă͂��Ȃ������B�[�������鍇�ӎ����Ɉᔽ�����Ƃ��ăg���v���E�|�C���g���t��i���A���łɎx���������ɈԎӗ����v���X���ĕԊ҂���悤���߂��B������g�����i�ׁh�̎n�܂�ł���B
�@���̑����Ɍ����������̂́A2003�N9��25���B�ٌ�m���ٌ��p�̐����ΏۂƂȂ��Ƃɒ��肵�Ă���ł�2�N�ȏ�A�g�����X�A���j�A���g���v���E�|�C���g����g���͓I�Ȓ�ď��h������Ă��炾�Ɗ�4�N���o�߂��Ă����B
�@�j���[���[�N�ō��ق̃n�[�}���E�J�[�������́A4,408���[�h���琬�镶���ŁA���[�U�[�ł���g�����X�A���j�A�ɗL���ȓ��e�̔������������B����ɂ��A�g�����X�A���j�A�́A���łɃg���v���E�|�C���g�Ɏx�����Ă���������������邱�Ƃ��\�ɂȂ����i���Ȃ݂ɁACIO Magazine�č��łł́A�����҂ƂȂ������ЂɃR�����g�����߂����̂́A�g�����X�A���j�A��CIO�A�x���W���~���E�^�������܂߁A��R�����g�邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�s�[�v���\�t�g���R�����g�����ۂ��Ă���j�B
�@�����A�͂����āA���̍ٔ��ɐ^�̏��҂Ȃǂ���̂��낤���B�ԋ���F�߂�ꂽ�g�����X�A���j�A�ɂ��Ă��A5���̋t��i�̂���4���͊��p���ꂽ�B�B��F�߂�ꂽ�̂́u�_������v�ł���B�܂�A�������҂��g���݂���m��O�̏�ԁh�ɖ߂��������ɂ����Ȃ��̂��B���̊ԁA���ׂɗ��ꂽ4�N�Ԃ̍Ό��ƁA���̊Ԃɔ�₳�ꂽ�J��́A�����Ė߂��Ă��邱�Ƃ͂Ȃ��B

�V�J�S�����_�Ɋ�������IT�i�א��ٌ̕�m�A�q���[�h�E�X�^�[�����O���́u���炩���ߌ_�̓��e���ᖡ���A������Ǝ�������邾���ŁA�@��ł̏X�������͔����邱�Ƃ��ł���͂����v�Ɨ͐�����Bphoto by Jeff Sciortino
�@�\�t�g�E�F�A�E�v���W�F�N�g������i�ז��́A�������Ɏn�܂������Ƃł͂Ȃ��B�@���֘A�̖{���Ђ��Ƃ��A����͎R�قǏЉ��Ă���B
�@�L���ǂ���ł́A1979�N�Ƀi�V���i���E�L���b�V���E���W�X�^�[�iNCR�j���d�q�@�탁�[�J�[�A�`���b�g���X�E�V�X�e���Y����_��ᔽ�ői����ꂽ�P�[�X������B
�@�g���v���E�|�C���g�̃P�[�X�Ɠ��l�ANCR���_��ŕۏ����V�X�e�����������ɔ[�����邱�Ƃ��ł����A����䂦�Ƀ`���b�g���X����i������n���Ɋׂ����B
�@�܂��A1991�N�ɂ́A�����O�E���{���g���[�Y�i���݂̓I�����_�̃Q�g���j�N�X�̎P���ƂȂ�A�Q�g���j�N�X�E�����O�ɎЖ��ύX�j�̃T�[�r�X�E�X�^�b�t���A�Ƃ���X�|�[�c�E�N���j�b�N�ŃV�X�e�����C�����Ă���Œ��Ɍ����5�N���̗Տ��f�[�^�Ɖ�v�f�[�^��j�Ă��܂��Ƃ����g���́h�����������B���R�A�����O�͑i�����A�ٔ������璍�Ӌ`�����@�̎w�E����Ɏ������B
�@�g�i���Ɓh�ƌ�����قǂ̕č������ɁAIT�ɂ܂��i�ׂ̐��������̂͂��Ȃ����邪�A���Ƃ����́AIT�i�ׂɂ͑��̈�ʓI�Ȋ�Ƒi�ׂƂ͌���I�ȈႢ������Ǝw�E����B����͂��Ȃ킿�A�����̂قƂ�ǂ����O�̏�������Łu�\���ɔ�����ꂽ�v���̂���ł���Ƃ������Ƃ��B
�@�V�J�S�̖@���������A�}�b�`�E�V�F���X�g�E�t���[�h�E�f�l���o�[�O�E�A�����g�����[�x���V���^�C���ٌ̕�m�A�q���[�h�E�X�^�[�����O���͂����w�E����B
�@�u�����ҊԂ̌����̑�������炩���ߑz�肵�Ă������Ƃ́A�_��̎傽��ړI��1�����AIT�v���W�F�N�g�ɂ܂��_��̑����ŁA���ꂪ�܂������l������Ă��Ȃ��悤�Ɏv����v
�@�{�X�g���̖@���������A���L���b�V���E�Q�X�}�[���A�v�f�O���[�u�ٌ̕�m�A���[�E�Q�X�}�[�����A�X�^�[�����O���̈ӌ��ɓ�������B
�@�uIT�v���W�F�N�g�Ō��킳���_��̑����́A���e���ɂ܂�Ȃ����x���ɂ���B�Ȃ��ɂ́A�@���̏펯���܂����������Ă���Ƃ����v���Ȃ��悤�Ȍ_�������B�N�����\���h���K�͂̑��Ƃł���A�x���_�[���Ɉ���I�ɗL���Ȍ_��ɕ��C�ŏ������Ă���̂ɂ͋��������v�i�Q�X�}�[���j
�@�_��ɂ����āA�@�I�ȃ��X�N���l�����邱�Ɓ\�\���̖�ڂ�S���ׂ��́A�����܂ł��Ȃ����[�U�[����CIO�ł���B�X�^�[�����O�A�Q�X�}�[�̗����́A���X�N�𖢑R�ɉ��������@�͎��ɐg�߂ȂƂ���ɑ��݂���Ǝ咣����B
�@�u���[�U�[�̎��q��́A��������Ȃ��B�ɒ[�Ɍ����A�_�Ɂw���ꂪ�A���A���ɑ��ĐӔC���̂��x�Ƃ������������ق��2�A3�s�����邾���ŁA�@�I�ȃ��X�N�̓O���ƌ���̂��B1�̃p���O���t�����ŁA���S���h���̔����������镴������������̂�����A������������{���Ȃ���͂Ȃ����낤�v�i�X�^�[�����O���j
�@���ɁACIO���@�I�ȏ�����ӂ����Ƃ���A�ȉ���3�Ƃ���̃V�i���I���҂��Ă���B
�@�܂�1�ڂ́u����v�B����́A�D���Ɋׂ邱�ƂȂ��v���W�F�N�g���~�ςł���Ƃ����Ӗ��ŁACIO�ɂƂ��āu�s�K���̍K���v�Ƃ�������őP�̃V�i���I�ł���B�������e��̑�萻��U.S.�J���Ń}�[�P�e�B���O�S�����В����O���[�o��CIO�߂�V�F���[���E�N�C�b�V�����́A���āA���̒���ɂ���ē�ǂ��������o�������B�����́A�u�x���_�[�Ƃ̊W���A�v�w�W�Ɠ����B�ʂꂽ���Ȃ�������ƌ����āA�����Ȃ�ٔ����ɋ삯���ނ̂ł͂Ȃ��A�܂��̓J�E���Z���[�������Ă�������Ƙb���������ƂŁA�݂������ʂɏ��������̂�����邱�Ƃ��ł���v�Ɨ͐�����B
�@����Ŏ������܂�Ȃ��悤�ȏꍇ�A��2�̃V�i���I�Ƃ��čl������̂́u���فv�ł���B���Ȃ݂ɁA���̏ꍇ�́A�ؐl��؋��Ɋ�Â������ׂ��K�v�ƂȂ�A���ҁA�s�҂̌��_�Â���������x�Ȃ���邱�ƂɂȂ邽�߁A�P�Ȃ�u������v�Ƃ��������x���ɂƂǂ߂邱�Ƃ͓���B
�@����ł��Ȃ��A�o��������Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�A��3�̃V�i���I�\�\�u�i�ׁv�ւƓ˂��i�ނ��ƂɂȂ�B�v���鎞�Ԃ��R�X�g���傫���A�ꍇ�ɂ���Ă̓}�X���f�B�A�Ɏ��グ���A��Ƃ̃u�����h�E�C���[�W�����������ꂷ�炠��B�����܂ł��Ȃ��ACIO���ł������Ȃ���Ȃ�Ȃ��V�i���I���B
�@������ɂ���A�������ЂƂ��і@��ւƎ������܂��A���̌�ǂ�قǂ̓w�͂��Ă��A�_���[�W���Ȃ��Ƃ����ۏ͂Ȃ��BCIO�ɋ��߂���̂́A��ɋ�����3�̃V�i���I�Ɏ���O�̒i�K�\�\���Ȃ킿�_��̎��_�ŁA���S�������Ă����Ƃ������ƂȂ̂��B
�@����ɂ��Ă��A�i�������풃�ю��ł���A�O�q�����悤��IT�ɂ܂��i�ׂ������Ē������Ȃ��č��ɂ����āACIO���Ȃ��@�I�����ɐϋɓI�łȂ��̂��\�\�ǎ҂̕��X�������ƕs�v�c�Ɏv���Ă��邱�Ƃ��낤�B
�@���Ƃ́A���̍��{�I�ȗv���Ƃ��āA�ȉ���3��������B
�@�܂���1�́ACIO�������Č_��@�ɑa���A�Ȃ������̎����𑼂̌o�c�w�ɒm��ꂽ���Ȃ��Ƃ������݈ӎ��������Ă��邱�Ƃł���B
�@�u�ł��邱�ƂȂ�A��������Ȍ����͑��l�ɔC�������Ƃ����̂��ACIO�̖{���̂悤���B���ɁA���N�ɂ킽���ēw�͂𑱂��A�����̉��l���ؖ����邱�ƂŃg�b�v�ɏ��l�߂�CIO�قǁA�w���ʂ������x���Ƃɂ͔M�S�ł��w�����������x���Ƃɂ͂����ł��Ȃ��Ƃ����X����������v�i�Q�X�}�[���j
�@��2�̗v���́AIT�v���W�F�N�g�ɑ���y�ϓI�Ȃ��̂̌������B�j���[���[�N�̖@���������A�r�A�[�X���P�i�[�\���ɏ�������r���E�r�A�[�X���́A�����������ۂ��u���u�����}���X�v�Ƃ������t�ŕ\������B
�@�u�����A���ꂩ�猋�����悤�Ƃ����Ƃ��ɁA�����Ȃ��̐����̘b�������o���l�����Ȃ��̂Ɠ��l�ɁACIO���A���ꂩ��^�b�O��g�����Ƃ���x���_�[�ɑ��ẮA���ӎ��̂����Ɂg���X�����h�b�������X���ɂ���B���݂���M�p��������Ƃ����l�Ԃ̏K���̂Ȃ���ƂƂ�������v
�@��3�̗v���́ACIO���͂��߂Ƃ���������A�_��S�ʂ��e�Ђ�������Г��ٌ�m��O���̌ږ�ٌ�m�ȂǁA����ٌ̕�m�Ɉ��Ղɂ䂾�˂Ă���Ƃ������Ƃł���B�m���ɁA�u�_�������ł���̂�����ő���Ɋ��p���悤�v�Ƃ����Ӑ}�͗����ł��邪�A���������g�������ٌ�m�h�̂��ׂĂ��AIT�v���W�F�N�g�̌_��ɂ��ĖL�x�Ȍo���ƒm���������Ă���킯�ł͂Ȃ��B
�@���ی���ЁA�}�[�`�����c���r�W�l�X�����Y���ݕی��̑OCEO�A�`���[���[�E�^���}�b�W���́A���́g�ٌ�m�C���h�̎p�����Ƃ������䂦�ɁA�@��Ɉ�������o���ꂽ�ꂢ�o�������B
�@�u�n�[�o�[�h�呲�̎Г��ٌ�m���g���̂ł͂Ȃ��A����2���h���������ă\�t�g�E�F�A���ٌ̕�m���ĂсA�_����e���l�߂Ă���A�ٔ��͔�����ꂽ�͂����v�ƁA�����͍��ł����������B������Ȃ��l�q���B
�@���āA�G�C�u���n���E�����J�[���哝�̂́u�ٌ엿��o��A��₵�����ԂȂǂ��l����A�ٔ��ɏ����Ă��A���ۂɂ͔s�҂ɂȂ邱�Ƃ������v�ƌ�������Ƃ����邪�A�^���}�b�W���́A���̌��t�̈Ӗ���g�������Ċw�Ԃ��ƂƂȂ����悤���B
�@�}�[�`�����c���r�W�l�X�����Y���ݕی���CEO�ɏA�C���ĊԂ��Ȃ�����A�����́A����c�Ǝx���\�t�g�E�F�A�ɒ��ڂ����B�J���x���_�[�i���݂͓|�Y�j�ɐ��������߁A���̓��e�ɂ��[�����������́A�擪�ɗ����ē��������[�h�����B�����A�����V�X�e������������ƁA�����͓����̍l�����傫�Ȍ����݈Ⴂ���������Ƃ��v���m�炳�ꂽ�B
�@�u�o���オ�����V�X�e���́A�܂Ƃ��ɂ��瓮���Ȃ��Ђǂ��㕨�������B���̂����A�x���_�[���̎В��͎���̃~�X�͔F�߂Ȃ�����A�w�����ƒ������炠��25���h���~�����x�Ȃǂƌ����̂��B�w�����ɖ����Œ����B�łȂ�����i����x�Ǝ��͓˂��Ԃ����B����Ƒ���́A�w�@��ŏ��ٌ͕̂�m���������x�Ǝ̂Ă���ӂ�f���A�������o�čs�����̂��B����Ȃ��ƂɁA�ނ�������Ō�̈ꌾ�������^���������v�i�^���}�b�W���j
�@�^���}�b�W���́A���̖����������邽�߂ɁA���قɎ������ނ��Ƃɂ����B�؋������낦�A�_��CIO���͂��߂Ƃ���ؐl�����̎�z��i�߂钆�ŁA�����́u�����͊ԈႢ�Ȃ��v�Ƃ̊m�M��Ɏ������Ƃ����B�����A���͂����ȒP�ɂ͉^�Ȃ������B�ٌ�m��Ӓ�l�������̌_�ׂĂ��������ɁA���́A�[���ƌ����Ɋւ���������A�_�̒����炷���ۂ蔲�������Ă��邱�Ƃ����������̂��B
�@�����Ƃ��A���̒��قł́A�x���_�[�������܂�ɂ����e���ȑΉ����Ƃ��Ă������Ƃ�����A�^���}�b�W���͖����g�����h�邱�Ƃ��ł����B�����A�l������25���h���̔������̂����A15���h���ٌ͕�m��ւ̕�V�֏[�Ă��A����ƂɎc�����̂͂킸��10���h���B���łɎx�����ς݃\�t�g�E�F�A�E���C�Z���X���ɁA�����́g�F�������h���x�̌��Ԃ�������ł������B�u���������炩�ɐ������̂ɍٔ��ő���˂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃقǖ��ʂȂ��Ƃ͂Ȃ��B���R�̌����邽�߂ɒlj��̃R�X�g�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂�����v�ƁA�����͉����̕\����ׂ�B
�@���ہA���[�U�[�ɂƂ��āA�ٔ����v���X�ɓ������Ƃ͂قƂ�ǂȂ��BIT�i�ׂ𐔑����S������ٌ�m���A���̓_�ɂ��Ă͓������F�߂Ă���B
�@�ߋ���50���ȏ��IT�i�ׂɒ��ِl�Ƃ��Čg������o�������ٌ�m�̃g�r�[ B. �}�[�]�[�N���́A�u�ٔ��́A��̓ǂ߂Ȃ��킢�ł��邤���ɁA�^�C�~���O���ԈႦ��ƁA���A��ƃC���[�W�̎��ĂɂȂ���B�������ACIO���g�ɂƂ��Ă��A����̎��s�����ɂ���킯������A���X�N�͂���߂đ傫���v�Ɨ͐�����B
�@�����͈ȑO�A���[�U�[���x���_�[�ɑ��A1,300���h���̑��Q���������߂��i�ׂ�S�������o��������B���[�U�[���͓��R�Ȃ��珟�i���m�M���Ă������̂́A�t�^���J���Ă݂�ƁA�؋��̎��W�����S�łȂ��������Ƃ������Ĕs�i�ƂȂ����B���̃��[�U�[��Ƃ͌��ǁA1,300���h�������߂��Ȃ����������łȂ��A�t��i�ɂ��150���h�����x�����n���Ɋׂ����Ƃ����B�ٔ��������Ɂg�����h�ł��邩�������D��ł���ƌ�����B
�@�\�t�g�E�F�A�i�ׂ̘_�������M�����o�������m�[�X�e�L�T�X��w�����̃g�[�}�X�E���`���[�Y�����A�i�ׂɖ��邢�����������������Ƃ͍���Ǝw�E����B�������g�A���āA����\�t�g�E�F�A�ٔ��̊Ӓ�l���������ۂɁA�؋����ׂɉ��X�Ǝ��Ԃ��₷�����Ɍ��C�������Ă��̎d������蓊���Ă��܂����o��������B
�@�u�l���Ă݂Ăق����B����300�h���ٌ̕�m4�l�ƁA����250�h���̎��\�\��̑�l��5�l���������āA�R���s���[�^���Ɏ��߂�ꂽ�f�[�^�A����ɂ�1�������̎菑���̃����̎R����A���肪�s���ɂȂ�悤�ȏ؋����Ȃ����ǂ������A���X�ƒ��ׂ�̂��B�ٔ��Ƃ͂����������̂Ȃ̂��v
�@���������؋��W�߂́A�u�R�X�g�̃u���b�N�z�[���v�i�X�^�[�����O���j�ƌ�����قǁA��Ƃ̎��v����������B�X�^�[�����O�����肪��������̒��ɂ́A���N�̊��ԂƐ���̕����A���\�l�̏ؐl��p�ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�Ȓ�������������Ƃ����B
�@�ȏ�̂悤�ȑi�ׂɂ܂��������Ă���ƁAU.S.�J���̃N�C�b�V���������������̂́A����߂čK�^�ȃP�[�X���������Ƃ�������B
�@�����́A�q�ɊǗ��\�t�g�E�F�A�̓����v���W�F�N�g��i�߂Ă���Œ��A���̍s����ɈÉ_�����ꍞ�߂Ă��邱�Ƃ��@�m�����B���̃v���W�F�N�g�ł́A���v��10�{�̃\�t�g�E�F�A������\�肾�������A�ŏ��ɔ[�����ꂽ2�{�̃p�t�H�[�}���X�����܂�ɂ����z�Ƃ�������Ă����̂��B�����AU.S.�J�����A�x���_�[�����A���̃v���W�F�N�g�̓�����y���������Ă����̂ł���B
�@���̉e���ɂ��A�v���W�F�N�g�S�̂̐i�s���x��n�߂�ƁAU.S.�J���̎Г��ɂ́A��Ăɋْ����������B���[�U�[�A�x���_�[�o���̎Q���̉��ŊJ����錎��1�x�̒���c�̏���A�u�Ί�1�Ȃ������ȃ��[�h�v�i�N�C�b�V�����j�ɕ�܂ꂽ�Ƃ����B�i�ׂ֔��W����͕̂K���\�\�����͂�����������v�����Ƃ����B
�@���������Ȃ��A�N�C�b�V�����́A��v���Ă����B�x���_�[���̒S���҂�1��1�Řb��������������Ƃɂ����̂ł���B����A�N�C�b�V�������g������l�Ƃ��Ă̖������ďo���킯���B
�@�����́g����l�h�Ƃ��Ă̏��d���́A�S���҂Ƃ̃f�B�i�[�ł������B�������A�d���̘b�͈�ؔ����B�Ƒ����A�D���ȉ��y�\�\�H���ƂƂ��ɁA���������Ȃ��b�����Ȃ���A�݂��ɐe�r��[�ߍ������Ƃ����B
�@�u�U��Ԃ��Ă݂�A2�N�Ԃ���������ɓ����Ă��Ȃ���A���݂��ɐS�ꃊ���b�N�X���ĉ�b���������Ƃ͈�x���Ȃ������̂��v�i�N�C�b�V�����j
�@�����A�N�C�b�V�����́A���炽�߂Ă��̒S���҂Ɖ���������B�����ŁA�u��X�̐�����j��ł���v���͂����������Ȃ̂��낤���v�Ƃ����P�������Ȏ��₩�璲����n�߂��̂ł���B�O��̌𗬂��������̂��A2�l�́A�ߋ��̃v���W�F�N�g�̒��Ŋ��������Ƃ���炢�b���������ƂŁA�������̎����������������Ƃɐ��������Ƃ����B
�@�u���Ƃ͂ƌ����A���������ȔF���̂��ꂪ�����������B�����ɁA�R�~���j�P�[�V�����̌��@�������A���̊Ԃɂ����Ђ̊Ԃɐ[���a���o���Ă��܂��Ă����̂��v�i�N�C�b�V�����j
�@U.S.�J���ƃx���_�[�́A����̃v���W�F�N�g�̋O���C���̂�����ɂ��āA�V���Ɍ_�����킷���Ƃɍ��ӁB�i�ׂ͉������A�v���W�F�N�g�͖����ɕی삳��邱�ƂƂȂ����B���R�Ȃ���A���̌�̃v���W�F�N�g�͂���߂ď����ɐ��ڂ��A�c��8�{�̃\�t�g�E�F�A�́A�킸��1�N�ł��ׂĊ��������B�ŏ��� 2�{�𗧂��グ��̂�1�N�����������Ƃ��l����A�g����h�͂��Ȃ�̌��ʂ��グ�邱�Ƃ��ł����ƌ����邾�낤�B
�@�N�C�b�V�����́A���̌o������A�u�v���W�F�N�g�Ɏ�肩����O�̒i�K�ŁACIO���g���A��Q�ɓ˂����������ꍇ�ɂǂ����邩�ɂ��āA�l��������Ă����K�v������B�ꍇ�ɂ���ẮA��O�҂�����������ɂ�������������o��������Ă������ق����悢���낤�v�ƁA���ׂĂ�CIO�ɑ��ăA�h�o�C�X��B
�@U.S.�J���̎���́ACIO���炪����l�ɂȂ�Ƃ����A����߂Ē������P�[�X�ł͂��邪�A������ɂ���A���v���O�̃v���W�F�N�g��@�I��i�ŋ~�����Ƃ���ꍇ�A���̒���ȊO�ɑI�����͂Ȃ��B
�@�������ŁA���݂͒���l�Ƃ��Ęr��U�邤�E�B���A���E�}�N�h�i���h�����A�N�C�b�V�������Ƃ����A�v���[�`�Ɠ��l�ɁA����ɗՂލۂɁA�܂��̓����b�N�X������ԂŃ��[�U�[���ƃx���_�[�����݂��ɗ����Ɉӌ����������邱�Ƃ̂ł�����𐮂��邱�ƂɐS���𒍂��ł���Ƃ����B
�@�u���̏ꍇ�́ACIO�ȂǗ����̐ӔC�҂��W�߂��W���C���g�E�Z�b�V��������n�߂邱�Ƃɂ��Ă���B�܂��ٌ�m�̈ӌ����A���ɐӔC�҂ɂł��邾������Ȗ@���p����g�킸�Ɍ����ɂ��Ęb��������킯���v�i�}�N�h�i���h���j
�@�����ɂ��ƁA���̍ŏ��̃~�[�e�B���O��A���҂͂�������ʁX�̕����ɕ�����A�܂�Ō������̌Z��ɒ�����𑣂��e�̂悤�ɒ���l�����ꂼ��̕������s��������̂��Ƃ����B
�@�u�܂荇��������ꂻ���ȏ�ԂɂȂ�����A�b���l�߂ĕ]���z�����߂Ă������ƂɂȂ�B�܂��A�w������͖@��ł����٘_���邾�낤�B����ɑ��A���Ȃ��͂ǂ��R�ق���̂��x�ȂǂƘb�������A�����Ē��ق�i�ׂ܂Ŏ������܂��ɍςމ�����A��̓I�ȏ������A�h�o�C�X����̂��v�i�����j
�@�}�N�h�i���h���ɂƂ��āA����Ƃ͂��Ȃ킿�g�����h�ł͂Ȃ��A�����悢�����֓������߂́g�U���h�ł���B�����́ACIO�ɑ��Ď��̂悤�ɑi����B
�@�u���ق�i�ׂ��ƁA����������A����������A���̂����������̂����O�̖ڂɂ��炳��邱�Ƃ������B�����A����̒i�K�ł���A�܂��A���Ԃ͏C���\���B���҂��Ë��_��͍�����Ƃ����̂́A�ꌩ����Ɠ���Ȃ悤�ɂ��v���邾�낤���A���́A���̉ߒ��ŋ��ʂ̗��v�������邱�Ƃ͋����قǑ����̂��B�x���_�[�ւ̕s�M���œ{��S���ɔ������Ƃ��Ă��A�܂��̓O�b�Ƃ��炦�Ē���̉\����T�邱�Ɓ\�\���ꂪ�ACIO��������ׂ������ł��낤�v
�@�u����Ȑ킢���v�\�\�f�g���C�g�n�قŊJ���ꂽIDX�V�X�e���Y�ƃZ���g�E�W�����E�w���X�E�V�X�e���Ƃ̑i�ׂŁA�����٘_�̋x�e���ԂɁA�X�^�[�����O���͗���銾���ʂ����Ȃ��炻��������B
�@���̑i�ׂ́A����Ë@�փZ���g�E�W�����E�w���X���A�\�t�g�E�F�A�E�x���_�[��IDX�Ɉ˗����Ă����v���W�F�N�g�������I�Ɏ���������Ƃ��āA IDX����i�����N�����ꂽ���Ƃɒ[�������̂ł���BIDX���̎咣�ɂ��ƁA7�̕a�@��60�ȏ�̐f�Ï����V�[�����X�ɘA�g������Տ����V�X�e�������邱�Ƃɍ��ӂ��Ă����Z���g�E�W�����E�w���X���A�g������h�𗝗R�ɁA���j��˔@�ύX�����Ƃ���Ă���B�X�^�[�����O���́A�������ł���IDX �̎�C�ٌ�m���B
�@���̓��A�X�^�[�����O�����ٔ�����K�ꂽ���R�́A����L�͂ȏؐl�����₷�邽�߂ł������B���̏ؐl�́A�ߋ�3�N�Ԃ�3�x�A�،���ɗ����A�����̑O�Ő鐾�،����Ă����B�ؐl�̖��́A�N���E�f�B�A�E�A�������B�X�^�[�����O���Ƃ́g�G�ΊW�h�ɂ���Z���g�E�W�����E�w���X�E�V�X�e���ɋΖ����錻���� CIO�ł���B
�@�u�،���ɗ��������CIO�̎p�́A��X�ٌ�m���猩�Ă��ɁX�����v�ƁA����̔O�������X�^�[�����O���B
�@�v���W�F�N�g�̉~���Ȑ��s���A����Ƃ��،��䂩�\�\������̓�����ނ��ƂɂȂ邩�́ACIO���g�̎��g�ݕ��ɂ������Ă���B![]()
�@
�R�F��含����`�c�q
�@�E�@�`�c�q�̌���
�i�@���x���v�̒��ŁA�`�c�q�@�i�u�ٔ��O���������葱�̗��p�̑��i�Ɋւ���@��(�ȉ��A�`�c�q�@)�j�����肳��A���̐�含�������Ƒԕʂ̐ݗ��ł��̎Y�����������悤�ɂȂ����B
�ŋ߂ł́A�u���ƍĐ��`�c�q�v�A�u��Â`�c�q�v�A�u���Z�`�c�q�v�A�u�X�|�[�c���كZ���^�[�v�u���������Z���^�[�̕��������ψ���ɂ��`�c�q�v�����V���ڂɂ���悤�ɂȂ����B
�܂��A
�@���ȔF�̂��Ɓu�����c�������@�l�㎖����������i��Õ������k�Z���^�[�j�v�A�u�Љ�ی��J���m��i�ИJ�m��J�����������Z���^�[�j�v��u�y�n�Ɖ������m��i���E��葊�k�Z���^�[�j�v�u�����c�������@�l���w����i���w�g���u�������@�ցj�v���@��T�O�̋@�ւŋƖ����L�m���ƌ���ڐ��Ō��鋭�݂������������݂���悤�ɂȂ����B
���Z���삾���ł��A�܂����̐�含���W�@�ւ��A�����I�Ȃ`�c�q�@�ւƂ��Ċ������J�n���A�i��s�Ƃ�Ђ����k���A�M�����k���A�i�Ёj�����ی�����E�����ی����k���A�����ق��k���A�،���������E���k�Z���^�[�A���{���i�敨�������k�Z���^�[
�����H�ƕi������i��������ψ���j�A�����������i������i��������ψ���j�j �Όڋq�g���u�������ɂ������Ă���B
IT����ɏœ_���i�������`�c�q�Ƃ��ẮA�u�i���jSOFTIC�v�ƁuIT-�`�c�q�Z���^�[�v������B
IT����̂�����v���O�����̕s��ɋN�����鎖�Ă͖{�M�ł͂܂����Ⴊ���Ȃ����A�͂��̔��Ⴉ��ٔ���@��ADR�u���ł̑�����l�@����Ɛ}�̂悤�ɂȂ�B
�@�i�v���O�����s��ɂ�����ٔ���@�^�ƕ��������^�FPDF116KB�j
�@�E�@�����������@�̑S�̑�
�@�����͓�҂̊Ԃł̂��߂��Ƃł���A���̉������@�ɂ�
�@
�@�@�@�@�@���(avoidance)�A
�@�@�@�@�A���Ό���(negotiation)�A
�@�@�@�@�B����(mediation)�A
�@�@�@�@�C����(arbitration)�A
�@�@�@�@�D�i��(litigation)�A
�@�@�@�@�E����(fight)
�̕��@������Ƃ����B���ꂼ��̕��@�𐋍s����ɂ͎Q���҂̍\���Ɖ����ւ̃A�v���[�`�̈Ⴂ������B
�@�@�@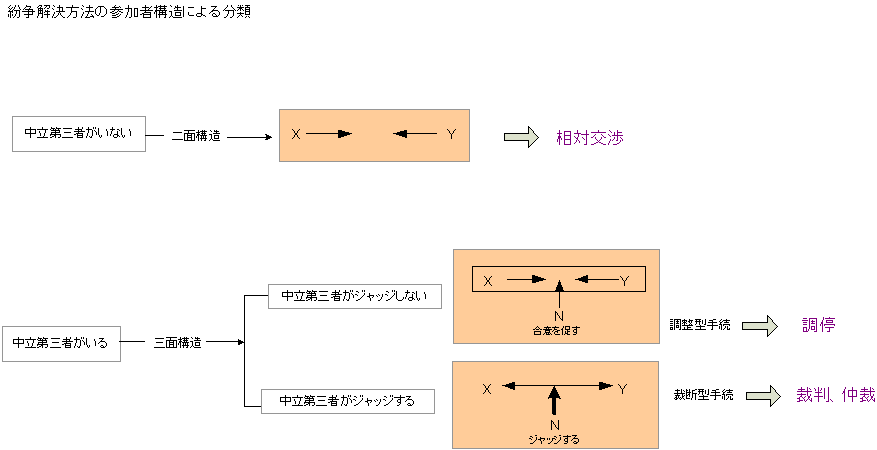
�����āA������������ւ̃A�v���[�`�Ƃ��Ă�
| �����I�A�v���[�` | �����I�A�v���[�` | |
| ���� | �� | �� |
| ����A���� | - | - |
| ���i�^����/����������^���� | �~ | �� |
| �]���^����E���v���^���� | �� | �~ |
| ���� | �� | �~ |
| �i�� | �� | �~ |
�i�ȊO�̎O�ʍ\���葱�����ٔ��O���������i�`�c�q;Alternative Dispute Resolution�j�Ə̂��B
�`�c�q��̌n�I�ɉ���������̂ɁA�w�`�c�q���_�Ǝ��H�x�a�c�m�l�ҁ@�L��t���̗Ǐ�������B
�@�w�p�I�������i�s���ł��邪�A
�@�@�@�u�ˈ����l��w���f�B�G�[�V�������������v�A
�@�@�@�u�@���x���v�Ɛ�[�e�N�m���W�[�v������A
�@�C�O�̃��f�B�G�[�V���������́A
�@�@�@�uNPO���{�����\�h�Z���^�[�v�A
�@�@�@�ٌ�m���V�P�v���ɂ��NY Mediation Center
���Љ��Ă���B
�S�FADR�Ƒ��̕����v���Z�X�F
���s���i��(�s������)�̈ʒu�Â��Ɖۑ�
�@
�܂��A�n���ٔ����ői�Ҏ��g�̎��Ăɑ���u�K�i���v�f����邱�ƂɂȂ�B
����͑i��O�u��`�ɒ�`���ꂽ�u�@�I�ی�ɉ������闘�v�����邩�H�v�Ŕ��f����A�s���ɒ��ڌW�鎖�Ăɂ��Ă͍s�������i�ז@��s���s���R���@�̊�Ői�߂���B
�@
�s���F������s���F���Ǝ��s�E���s�i��s�A���z�ƁA�s�����m���j�ɌW���ɏ���ҁE���p�҂Ƃ̕����ɂ��ẮA���ꂼ��̋@�ցi�ƊE���ݒu�������j�g�D����ADR�Z���^�[�������������A���̃v���Z�X��I�����邱�ƂɂȂ�B
IT���⎩�R�����ȂǍŋ߂̕����́A�ڂɌ����Ȃ����V�������l���ɂ����̂�l�Ԃ̒�����l�̎��R�ςɊ�Â����̂������B��@�̊���łǂ̒��x�̔�Q���̎�E���x���q�ϓI�ɐ����ł���ړx���K�v�ł���B
���̊��n�o���A�W�҂��[���ł���u�����鉻�v�̕ǂ����z���Ȃ���s�������̐^�̉����͂قlj����B����͖@�I���_����̊����������Ă���ꍇ�A�ٔ����́w���̌��@�y�і@���݂̂ɍS�������x�i���@76��3���j�A�����Ɣ퍐�i���̏ꍇ�A����n���s�����j�̎咣�ɂ��Č��@�⑼�̖@���ɏƂ炵�Ĕ��f�ɖ������Ƃ��́A�ٔ����́u�ǐS�v�ɏ]���Ĕ��f����ƒ�߂��āA���ȓ��S�̗ǎ��Ɠ����ςɏ]�����ƥ���Ƃ̔���(�ō���1948/11/17)������A�ٔ������g�̉��l���A�p���_�C���̕ϗe��������̂ŕ����̂��Ƃł͂Ȃ��B
�܂����Ă͐��I�̈�Ƃ���s���́u�R�c��x�v�ŒS�ۂ���Ă���̂ŁA��C�����͏��Ȃ��B�i�O�q�̕ǂ����藧�ɑ���̎��ԂƘJ�͂�v���Ă���̂Ōo�ύ����I�ɑi��i���Ƃ锻�f�܂ōs���Ȃ��j�܂����ɕK�v�ȏ؋��͎��炪�s���Ă��Ȃ��̂ŏ؋��͑��葤�ɂ��̑唼�������A����̉ʂď���J���̌��肪���ӓI�Ƃ��v���闝�R�ŊJ������Ȃ��P�[�X�܂łłĂ���̂Ō����N�i��ⓚ�ُ��E�ӌ��Ӓ菑�쐬�ő���ȓw�͂�v����B
���̂悤�Ȃ��Ƃ���A����
�@�@�E�s�������i�ז@�̈ꕔ�����@���}��(PDF121KB)
�@�@�E�s���s���R���@���ŏI�����F�����ꔪ�N�Z�������@����ܔ���
�@�@�E�R�c��̐����������Ɋւ����{�v��F��11�4�27�t�c�����@�@
�Ƃ̕������͎�����Ă��邪�A���̎��{�́u�i�@���v�̔g�v����������A�x�X�Ƃ��Đi�����Ă��Ȃ��B
�@�@�@�i�Q�ƁG�č����O���g���[�E�V�X�e���̊�{�I�����Ɩ��_�j
���d�g�s���i�ׁiPLC�ًc�\���R���j�ɂ݂��Y�̉ߒ�
�@
���z�ɂ�����u�i�ό��v�����Ɠ��l�ȊT�O�ŁA�@���ɖ���������Ă��Ȃ��u�ՐÂȊ��ł̓d�g���挠�v�����߂��s���i�ׂ��t����Ă���B
�d�g�d�q�s���ɂ����鑍���ȓd�g�R�c��A�d�͐��ʐM�yPLC�FPower Line Communications�z���p�̖��ŁA��U�A�����F�߂��^���F���������������s�ׂ������B���̗��R�ɂ��ċ��ߖ������߂��ًc�\�����ĐR�����i�߂��Ă���B
�@�@�@�@�@�E����PLC�@�ًc�\��������
���̐R�c�ψ��̍\����R�c�i�s�A�R�c���e���A�����ґ����_�ɗ��r���u�����v���肫�̗��O�Ɋ�����n�_���}�����m��ȐR�c�ł���A���{�͌���A���ۓI�ɂ��Ǘ������B���̎�̍s���i�ׂɂɂ���u�s���̍s���Ă��邱�Ƃ͌����I�ɐ������v�Ƃ��������ɂƂ���A������Z�p�⍡�����͐������Ƃ����ϑz����l�������āA�V�������_�̌n��V�������l�����n���ł��Ȃ��p���d���̂��������Ă���B
�����Ă͗ޕʂ���ƍs���i�ׂɂ�����u��ϑi�ׁv�̂悤�Ɏv���邪�A�����̐^�̊肢�́A����u���R��Y�ł���d�g�̒Z�g�т���肽���v�Ƃ̐Ȃ�l�Ԃ̔����o�Ɋ�Â��_���W�J�ł���B���̔��f�����i�����g�p����CM�d�����f���ɂ��^���F�蔻��́A���f�������̂��̂ɖ�肪����A���{�����̑S�Ă̏Z�������f�ł��Ȃ����_���ł���A����̐l�H�I�G��������ƂȂ�悤�Ȗ��ł���B���f�����ɂ��F��͍s���ׂ��łȂ��Ƃ���j�����ł���Ƃ���B�R�c�ߒ��̃v���Z�X���̗��_�I���B���ɂ����܂܂ł́A�����ɉЍ����c�����ƂɂȂ�Ǝ咣�����̂ł���B
�@
���̋K���E��ł͌�������f�ɂȂ�A���E�̒����ɂ�����Ȃ��ƌ����u�q�ϑi�ׁv�Əd�����鎖�Ăł���̂ŐR�����������ɂ߂Ă���B�@
�i�אl�B�́A�����̋ǂ̔���ȓd�g���A�m�C�Y�̒�����M���𒊏o���i���t�B���^�[�ŔF�������ʂ̎G�����ꂷ��̓d�g���x�j�C�O�̐��̐��A�������烏�N���N����������A����炪���H�n�ւ̓��ƂȂ�����A�u�͂�Ԃ��v�œd�g�r����Ԃ�46���Ԃ��F���G���̒�����M�������o�����u���{�̍��v�����܂�Ă���B
����ȃA�}�`���A���������D����l�B���A�d�g�R�c��̓d�g�s���ɗ����������Ă��錴���c�̋�Y������B
�@�@�E�{�MPLC�s���i�ׁ@
�@�@�@�@�@�@�@�c�O�ł��邪�R�����ł���̂ŁA���̏������ނ͌f�ڂ��Ă��Ȃ��B�܂����͏��J�������ɍs�������s�J�����肪�Ȃ���Ă���
�@ �E�č��ł́APLC�s���i�ׂŌ���ARRL�����i�����B
�@�@�@�@ ����ARRL ��FCC �ɒ�o�����u�W�Q�g�������v���Q�l�ɂȂ�B(����2�D53MB)
����s���i�������ŁA���ۓI�ɂǂ̂悤�Ɉ������قȂ邩�i�{�M�̐����@�Љ�ƕč��̔���@�Љ��j�̔�r�����̍D�ޗ��ƂȂ�B
����14�N���瑱��������PLC���������ȐR�c���ʌ��\ �� ���{�A�}�`���A�����A���̉���PLC���Ή��E�������������B
�@�@�@�@�@
�d�C�ʐM����ł͑����ȂɁu�d�C�ʐM�������������v���݂����A����/����/���\/�����Ȃǂ̎d�����s��ADR�g�D�����邪�A��ɍs���ɌW��d�g�d�q�@��̃T�v���C�T�C�h�ł���ƎҊԖ��������Ă���B
���ӁF���݁A�Z�p�I�A�[�L�e�L�`���[�͑S��������PLC�ł������O���pPLC����R�c���ł���B
�����ȐR�c��I�Ղɍ����|�����Ă���̂ŐR�c���T�������B
�ŋ߂̓��{�A�}�`���A�����A���̉��OPLC�ɑ���@�ւƂ��Ĕ��ΐ����͂܂��o�Ă��Ȃ��͗l�ł���B
�܂�
�R�c��ł́A�Z�p���̑O�ɐR�c��`�����̂��̂̐��x��J���݂���̂ł��̈�[��`���ipdf�G��1.06MB�j
�@�@�L�q�́A����24�4�21���݂ɂ��B
�@�@�@�i������\��JA1ELY��ދy������w�k�싳��PLC Report�A�����V���䗝�w���m��Ώy�����w����Q�Ƃ���)�B
�@�@
�@�@�@���Q�l�}���F�w���z�����x�@-�s���E�i�@�̕��각@�\���h��E���쏺�Y���@��g�V��2006�N11����
�@�@�@���Q�l�}���F�w�����X�N�w�x�s���̊C�̗��j�Ձ@�@�������q���@���{�]�_��
�@���Q�l�F�w�ŐV�m���Ɋ�Â������d�͐��ʐM�K���xEMCJ2011-143(2012-03)��A�k��
![]() ���̃y�[�W�̐擪��
���̃y�[�W�̐擪��
5:�u�����Ȉ���v�ł��邪�A����I�����R�c��i�̖閾���I
�@�@
�m�����ق́A���I�ʼnߋ��ɔ���̂Ȃ����_�ɂ��āA���Ƃ�����ɏڂ����ƊE�W�҂���L���ӌ������ƂƂ��A2014/1/23�ӌ���W���邱�ƂƂ����B
���{�̍ٔ������W�����̖����i�ׂ̐R���ň�ʂ̈ӌ����W���邱�Ƃ́A�u�����Ȉ���v�ł��邪�A����I�����R�c��i�̖閾���I�ł����B
�@�@�@�@�E�m�����ق̈ӌ���W
�����@���̖{�M�ɂ����@���̗��@�[�u�́A�Ƃ�����Βx�ꂪ���ł���B��Õ����ICT�V�X�e���Z�p�v�V�֘A�ł͓������ɐi���̃X�s�[�h�������A���ꂪ��Ƃ⍑�͂̍��ʉ��v���̑傫�ȗv�f�ƂȂ����B
�Ő�[����ł́A�����J���Ɛ��s���s���v�l���p�A���ەW���K�i�擾�����̔��W�̃L�[�t�@�N�^�[�ƂȂ�A�ǂ����Ă��R���t���N�g���N����B���̃R���t���N�g���ٔ��ʼn��������i���Ƃ�ƁA���R�̍����̋Z�p�͂����ߋ��̂��̂Ƃ��āu�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��v���ۂƂȂ��Ă���B
���ꂪ�܂������I���f���|�Ƃ�������E����i�@���������Ă���B
�]�_�Ƃ�w�҂̑�3�҂́A�����̈ӌ���\�����Ȃ��w����̐ςݏグ��҂x�p������A�Êς̎p�����������Ă���B
���i�E�Y�i�@���u�i�@���x���v�v�̋��т̒��Ŏ��c���ꂽ�ۑ�ł���B����ȕNJ��̒��ŁA�{�M�̋��ԂƂȂ��������i�ז@�̔��肪����Ȃ���A����̈ӌ���W�菇�͉���I�Ȉ���ݏo�����B
����̈ӌ���W�́A�ăA�b�v���Г��{�@�l�Ɗ؍��A���X���d�q�́wFRAND�錾�x�����铖���ҊԂ̉��߂��ꗂł��邪�A���̎픻��@���̕č��ł͗L�p�Ȃ锻�����݂���B
���̈��Twitter�Ђ́wTwitter�I���b�Z�[�W�V�X�e���x�̓������߂���wIPA���ӏ��FInnovator's Patent Agreement�x������B
����͓��������C�m�x�[�V�������t�ɑj�Q���Ă��܂��\�������O���āA��Ƃ���������h�q�̂��߂����g��Ȃ��悤�ɂ���ړI�ɂ����V���Ȏd�g�݂ł���B
�܂��AGoogle�Ђ�e-Book������č�NY�A�M�n�ق́hGoogle Books"�i�����ɂ݂�Denny Chin�������������Ƃ����@��ӌ����A��X�ɖ��邢��]��^��������ƂȂ��Ă���B
��[�Z�p����ɂ����邱�̂悤�ȃR���t���N�g�́A�{�M�ɂ�����c�_�ƃ_�C�i�~�b�N�ȃV�X�e�����O��W�J����č��Ƃɐ������x�̌���̔w�i�ɍ����I�F���̍����I�悵�Ă���Ǝv����B
�O�q��PLC�s���i�ׂ⌴�q�͎��̑i�ׂɌ�����u�i�@���������x�I�ȉۑ�v�������핶������B
�@�@�@�E�č����O���g���[�E�V�X�e���̊�{�I�����Ɩ��_
![]() ���̃y�[�W�̐擪��
���̃y�[�W�̐擪��

�@![]() �@�@��������uIT's-Prevention&Investigation�̓m�v��Top��
�@�@��������uIT's-Prevention&Investigation�̓m�v��Top��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Copyright�@© 1996-2014 by JA2ANX Naoki Inagaki. this HP all pages is ISSN 2187-5049